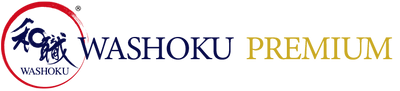日本で唯一残る広幅洋装シルクジャガード織物工場
石川県小松市に、日本で最後となった広幅洋装シルクジャガード織物工場があります。横幅150cmという広幅のシルクジャガード織機を使用する工場は、現在日本でここだけ。1960年代の織機が今も現役で稼働し、熟練職人によって希少な生地が織り続けられています。
1万本の経糸が要求する精密技術
シルクジャガード織りで最も困難とされるのが、1万本以上の経糸(たていと)を織機にセットする作業です。髪の毛よりも細いシルク糸を、一本一本手作業で正確な位置に配置していく必要があり、わずかなずれも許されません。
この作業には高度な技術と集中力が求められ、国内でも数少ない熟練職人だけが行うことができます。通常の生地と比較して約1.4倍のシルクを使用し、ジャガード織りによる凹凸が立体的で上質な仕上がりを実現しています。

日本各地の職人技術の結集
生地の完成には、複数の地域の専門技術が必要です:
- シルクジャガード織り
- 後染め技術による色付け
- 縫製加工
特に山形県米沢市で行われる「後染め」は、生地を織り上げてから染色する高度な技術で、先染めとは異なる深みのある色合いを実現します。
希少な技術の継承と、その価値
現在、日本国内で後染めによるシルクジャガード生地を手がける工場は、この石川県の小倉織物の工場が事実上最後となっています。1960年代の織機は部品の調達も困難で、この複雑な技術を習得できる職人も年々減少しています。
円安により輸入品価格が上昇する中、日本国内の高品質なものづくりに改めて注目が集まっています。機械化が進む現代において、手作業による生産から生まれる品質は、大量生産では決して実現できない価値を持っています。
唯一無二の美しさを手に
この希少なシルクジャガード生地で作られた扇子は、確かに高価かもしれません。しかし、1万本の経糸が織りなす立体的な美しさ、後染めによる深みのある色合い、そして日本各地の職人技術が結集した品質は、他では決して手に入らないものです。

ジャガード織りの凹凸が生み出す光と影の表情は、扇子を開くたびに異なる美しさを見せてくれます。これは単なる実用品を超えた、日本の伝統技術の結晶として、そして次の世代に受け継ぐべき文化遺産として、その価値を実感していただけるはずです。
失われゆく技術だからこそ、今しか手に入らない特別な美しさがここにあります。